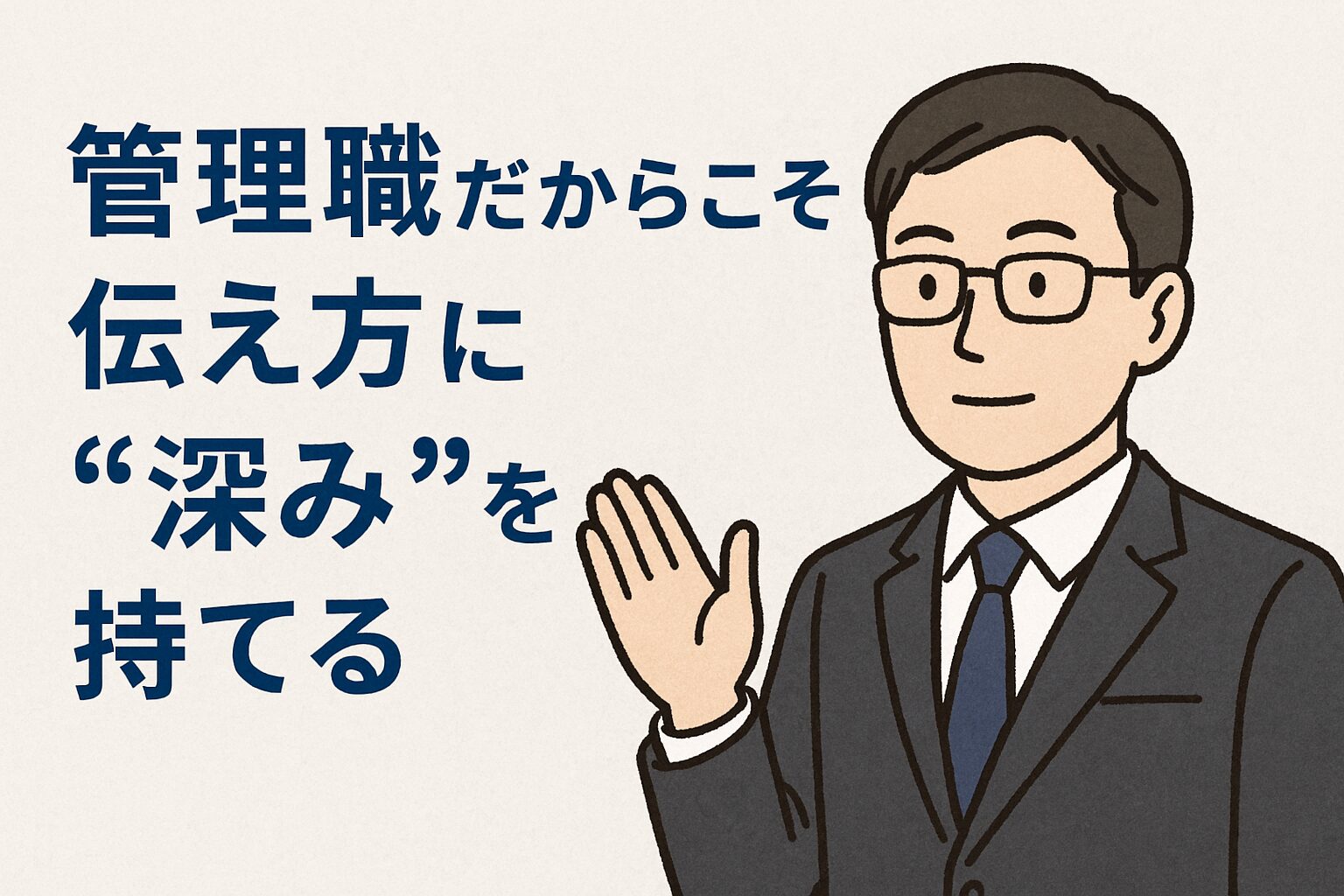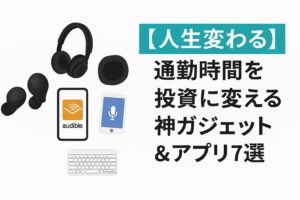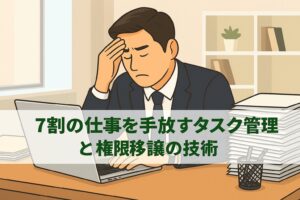40歳で管理職に昇進した私は、社会人としての経験には自信がありました。業務知識も、現場対応力も、それなりに磨いてきたつもりです。
しかし、いざ「部下を評価し、フィードバックを伝える立場」になったとき、思いがけない壁にぶつかりました。
「どう伝えれば、相手に響くのか?」 「厳しすぎてもダメ、優しすぎても伝わらない…」 「自分の言葉が、部下の成長やモチベーションに影響する」
そんな葛藤の中で、私は“伝え方”の重要性を痛感しました。
この記事では、40歳・新米管理職としてのリアルな体験をもとに、「評価・フィードバックの伝え方」について考えていきます。
よくあるギャップと戸惑い|“伝える”ことの難しさ
管理職になって初めて気づいたのは、「伝えること」と「伝わること」はまったく別物だという事実でした。
これまでのキャリアでは、同僚や上司とのやり取りは“横の関係”が中心。多少言葉が足りなくても、意図を汲み取ってもらえることが多かった。でも、管理職になると状況は一変します。
部下は、私の言葉を“評価”として受け取る、つまり、言い方ひとつで、モチベーションが上がることもあれば、落ち込むこともあるということです。
そのギャップに、私は戸惑いました。
実体験:研究報告へのフィードバックが、部下の意欲を削いだ瞬間
昇進して間もない頃、私はある若手研究員の試験報告書に目を通していました。新規化合物の安定性試験に関する内容でしたが、データの整理が甘く、考察も浅い。しかも、重要な条件変更の記録が抜けていたのです。
「これはまずい」と思った私は、すぐに個別面談を設定。
しかし、伝え方に悩んだ末、私はこう切り出してしまいました。
「この報告書、正直言って研究者としては未熟すぎる。これじゃあ再現性も信頼性も担保できないよ」
沈黙のあと、彼は小さく「すみません」とだけ答えました。
その後の数日間、彼の表情は曇りがちで、実験への積極性も見られなくなりました。
「まずかったかもしれない…」
そう思った私は、改めて彼と話す機会を設け、今度はこう伝えました。
「報告書の提出ありがとう。データの整理や条件記録に改善点はあるけれど、試験自体は丁寧に進めていたと思う。次回は、記録の精度を上げることで、より信頼性の高い報告になるはず。必要なら、フォーマットの見直しも一緒にやろう」
彼は少し驚いた顔をしたあと、「次はもっと意識して記録します」と前向きな返事をくれました。
この経験を通じて私は、「伝え方ひとつで、部下の受け止め方も、研究への姿勢も変わる」ということを身をもって学びました。
・専門性に頼りすぎて、言葉が鋭くなってしまう
➡改善点を伝えたつもりが、部下が萎縮してしまった。
・遠慮して曖昧な表現になってしまう
➡結局、何を改善すべきか伝わらず、同じミスが繰り返された。
・フィードバックが伝わっていない気がする
➡言葉は交わしたのに、行動が変わらない。
こうした戸惑いは、どんな職場でも起こり得るもの。
だからこそ、「伝え方」は管理職にとっての“技術”であり、“信頼構築の鍵”なのです。
評価・フィードバックの本質とは|“査定”ではなく“育成”のために
管理職になりたての頃、私は「評価=査定」「フィードバック=指摘」と捉えていました。
しかし、実際に部下と向き合う中で、その認識が大きく変わっていきました。
評価やフィードバックの本質は、単なる“点数付け”ではありません。
それは、部下の成長を促し、チームの信頼関係を築くための“対話”です。
評価の本質:事実に基づき、成長の方向性を示す
評価は、過去の行動を振り返るだけでなく、未来への期待を込めて示すものです。
研究開発の現場では、成果だけでなくプロセスや姿勢も評価対象に含めることで、部下の成長意欲を引き出すことができます。
感情や印象ではなく、具体的な事実に基づいて伝えることで、納得感と信頼が生まれます。
例:「〇〇の試験設計は、条件設定が明確で再現性が高かった。今後は、他の試験にもこの設計を応用してほしい」
フィードバックの本質:指摘ではなく、信頼のコミュニケーション
フィードバックは、改善点を伝えるだけでなく、良かった点を認識させることも含まれます。
一方的な通達ではなく、双方向の対話を意識することで、部下の主体性と安心感が育まれます。
「あなたの成長を本気で応援している」という姿勢が、言葉の重みを変えるのです。
例:「報告書の構成は改善の余地があるけれど、実験の進め方は丁寧だった。次回は構成面も一緒に見直してみよう」
管理職の言葉は“組織の空気”をつくる
管理職の言葉は、チームの雰囲気や文化に大きな影響を与えます。
何気ない一言が、部下のやる気を引き出すこともあれば、萎縮させてしまうこともある。
だからこそ、伝え方には責任と配慮が必要です。言葉を通じて、安心して挑戦できる空気を育てることが、管理職の大切な役割です。
例:「このアイデア、面白い視点だね。仮説の立て方に工夫が見える。ぜひチームでも共有してみよう」
実践テクニック:伝え方の型とコツ
評価・フィードバックの本質を理解しても、いざ伝える場面では迷いが生じるものです。
ここでは、実際のシーンに応じた“伝え方の型”と“コツ”を紹介します。
型を持つことで、言葉に自信が生まれ、部下との信頼関係も築きやすくなります。
| シーン | 伝え方の型 | コツ | 例文 |
|---|---|---|---|
| 成果を称えるとき | SBI法(Situation-Behavior-Impact) | 具体性と納得感を重視 | 「〇〇の試験設計(S)は、条件設定が明確で(B)、再現性の高いデータが得られた(I)」 |
| 改善点を伝えるとき | SBI+期待+支援 | 責めずに未来志向で伝える | 「報告書の構成が不明瞭だった(S)。記録の整理が不十分だった(B)。次回はフォーマットを見直して、私も一緒に確認するよ(I+支援)」 |
| 面談・1on1でのフィードバック | 傾聴+質問+共感 | 「最近の実験で感じていること、率直に聞かせてほしい。困っていることがあれば一緒に考えよう」 | 「最近の実験で感じていること、率直に聞かせてほしい。困っていることがあれば一緒に考えよう」 |
| チーム全体への声かけ | ポジティブ+具体+共有 | 「〇〇さんの仮説立てが秀逸だった。あの視点は他のプロジェクトにも活かせそう。ぜひ皆で参考にしよう」 | 「〇〇さんの仮説立てが秀逸だった。あの視点は他のプロジェクトにも活かせそう。ぜひ皆で参考にしよう」 |
このように、型とコツを意識することで、伝え方に“軸”が生まれます。
特に研究開発の現場では、論理性と人間性の両立が求められるため、言葉の選び方が成果にも影響します。
フィードバック文化を育てるために|信頼と成長が循環するチームへ
評価やフィードバックは、管理職から部下への一方通行ではなく、チーム全体で育てていく“文化”です。
研究開発の現場では、成果だけでなく仮説や失敗も共有されるからこそ、安心して意見を交わせる空気が不可欠です。
その空気をつくるのに大事な要素は、管理職の言葉と姿勢です。
日常の声かけを“フィードバックの種”にする
フィードバックというと、面談や評価面接など特別な場面を想像しがちですが、実は日常の何気ない声かけこそが、最も効果的なフィードバックの土壌になります。
「ありがとう」「助かったよ」「この視点、面白いね」といった言葉は、部下の行動を肯定し、次の挑戦への後押しになります。
研究開発の現場では、成果がすぐに出ないことも多いため、プロセスや姿勢を認める声かけがモチベーション維持に直結します。
管理職が日常的にポジティブな言葉をかけることで、フィードバックが自然に行き交う空気が育ちます。
自分もフィードバックを受ける姿勢を見せる
管理職が一方的に評価や指摘をするだけでは、部下との信頼関係は築けません。
むしろ、上司自身が「どうだった?」「改善点があれば教えて」と部下にフィードバックを求めることで、双方向の関係が生まれます。
研究開発のように専門性が高く、若手の視点が新しい発見につながる現場では、上司が“学ぶ姿勢”を見せることが重要です。
「上司も成長しようとしている」と感じてもらえることで、部下も安心して意見を言えるようになります。謙虚さと対話の姿勢が、チームの風通しを良くする鍵です。
「フィードバックは贈り物」という価値観を共有する
フィードバックは、相手の成長を願う“贈り物”です。
指摘や改善点を伝えることは、相手を否定するためではなく、可能性を広げるための行為。
この価値観をチームで共有することで、フィードバックを前向きに受け止める土壌が育ちます。
研究開発の現場では、仮説や失敗の共有が日常的に行われるため、安心して意見を交わせる文化が成果にも直結します。
管理職が「伝えること=育てること」という姿勢を持ち続けることで、フィードバックが信頼と成長の循環を生むチームへと進化していきます。
まとめ:管理職だからこそ、伝え方に“深み”を持てる
管理職としての経験年数に関係なく、「伝え方」はいつでも磨ける技術です。
キャリアの途中で管理職になった人も、専門職から転身した人も、それぞれの背景が“言葉の深み”につながります。
大切なのは、完璧な伝え方を目指すことではなく、部下の反応に耳を傾けながら、試行錯誤を重ねる姿勢です。
研究開発の現場でも、仮説と検証を繰り返すように、伝え方も実践の中で育っていきます。
一度のフィードバックで全てが変わるわけではありませんが、積み重ねた言葉は、確実に信頼と成長の土台になります。
あなたの管理職という立場だからこそ出せる“深み”と“温度”を込めた伝え方で、部下の背中を押していきましょう!